僕たちは福祉事業を会社という組織で運営しています。
そこで皆さんに会社という生命体の原理原則について理解してもらいたいと思って今日は書き綴ります。
まず株式会社は矛盾をはらむ生命体であるということです。
そのために理解しなければならないのは下記の3つです。
①市場の本能
これは「変わる」ということです。
今流行っているファッションと10年前に流行ったファッションは違いますよね。
タピオカ屋がいたるところにあった時代もいつのまにか過去のものとなりました。
障害者福祉サービスにおいてもニーズは多様化しています。
また社会保障は破綻するという話もあります。
税金で運営する我々のような事業は国家の構造が変化することで難しくなる可能性もあります。
②事業の本能
きれいごとを抜きにして、これは「利益の最大化」しかありません。
我々は福祉施設ですが、ただしい定義は福祉サービス業です。
利益が出せなかったら倒産します。
事業を存続させなければユーザー、社員(仲間)を不幸にします。
存続できないかもしれない事業に大切な人の人生を巻き込むべきではありません。
③組織の本能
組織は人の集合体です。
人(組織)の本能は「変わりたくない」です。
※人の本能についても述べだすと長くなるのでここでは割愛させていただきます。
参考記事→心理的ホメオスタシスについて
つまりこの本能に従うと会社というのは倒産するというのが当たり前ということになります。
事実、
会社を創業して10年以上の存続率は6.3%
20年後の存続率は0.3% です。
これは国が発表しているのでググってみてください。
まとめると会社という生命体は倒産する=存続できない生き物であるということです。
これを逆説的にとらえると
変化できる組織(人)は存続できる
変われない組織(人)は存続できない
ということなんです。
では変化できる組織をつくるために重要なことってなんだと思いますか?
それはカルチャーづくりです。
ではカルチャーってなんだと思いますか?
社風?文化?
なんか宗教臭く思われるかもしれませんが、
カルチャーの正しい意味というのは辞書で下記のように記載されています。
複数名により構成される社会の中で共有される考え方や価値基準のこと
1対1の関係性の中でもカルチャーというのはあるということです。
例えば2人で飲みに行って愚痴をこぼしあって飲む。
会社や社会が悪いよねと盛り上がる。
これがこの人たちの中でのカルチャーです。
例えば2人で飲みに行って互いの努力をたたえあう。
未来に向かって建設的に語り合う。
これもまたこの人たちのカルチャーです。
これが大勢となって、戦争をすることが大切だ正義だとなればそれもカルチャーです。
カルチャーづくりを間違えると大変なことになります。
会社という組織はカルチャーが統一されていないとチームになれません。
統一された考え方や統一された価値基準がチームには必要です。
だからこそ会社には行動指針というものが設定されています。
人事考課で行動指針の体現に対して非常に重きを置いているのはコレが理由です。
そしてこの行動指針は未来僕たちがどのようでありたいのか、どうあるべきなのかを体現するためのギャップ(差)を埋める手段でもあるということです。
現在の場所から未来に向かって行動するための手段です。
もう一度いいますが、手段です。
ややこしいこといいますが行動指針の体現は目的ではないということです。
だからこそ行動指針は定期的に見直す必要があって、つねに現在と未来との差を見つめなおす必要があるわけです。
ITスクールもデジラボも行動指針を再設定したほうがいいなと思っています。
こちらについてはまた改めて共有させてください。
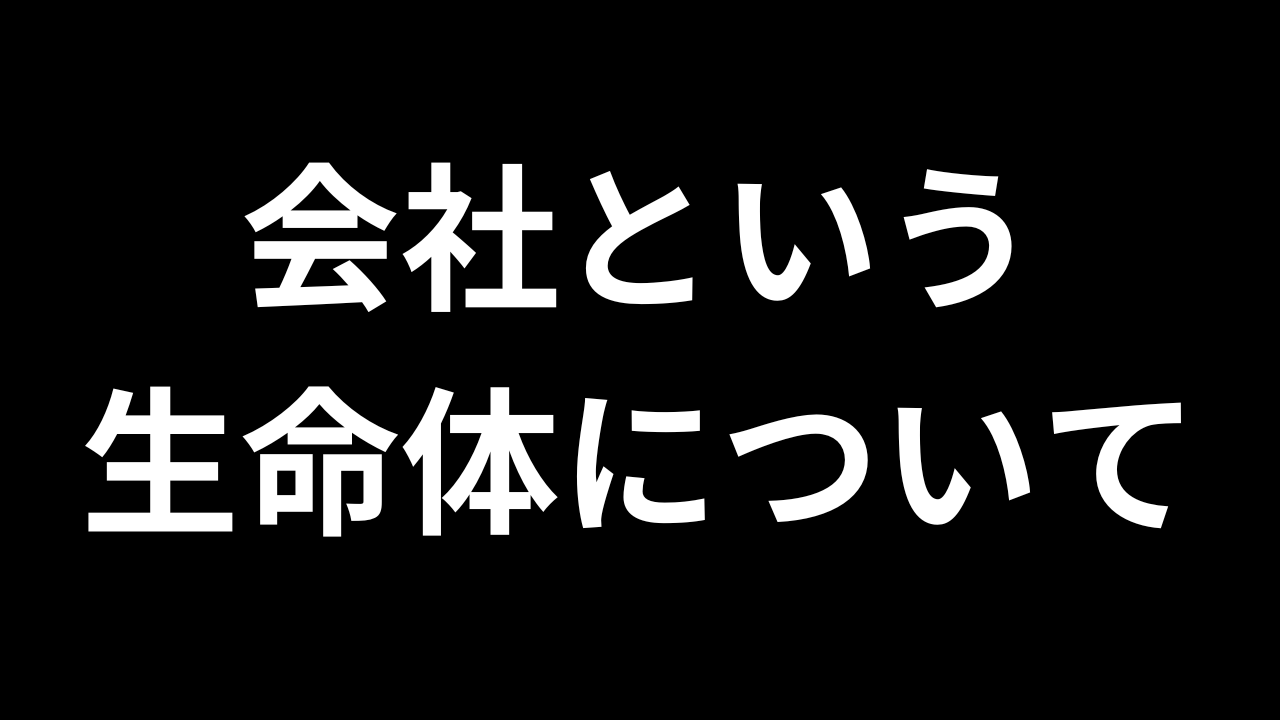
コメント