職場環境が楽しくないと働いていても楽しくないですよね。
僕は一緒に働いてくださっている皆さんには気持ちよく働いてもらいたいと思っています。
そこでいいチームをつくるために大切にしたいことを今日はブログにしたいと思います。
いいチームには3つの共通がある。
共通目標
その名の通り、共通の目標です。
会社でいえば会社のビジョンでしょうか。
団体競技でいえば高校野球甲子園優勝する!サッカーワールドカップで優勝する!といった共通の目標です。
皆が同じ目標を持てているかどうか、どうせ無理だろって思っている人がいればダメです。
言葉だけが一人歩きするのではなく、全員が心からその目標を達成したいと思えるか。とても重要です。
共通言語
これは共通の価値観や行動基準を表すために必要です。
例えばディズニーランドでは従業員のことをキャストと呼びます。
そして職場のことをステージといます。
キャスト=演技者、ステージ=舞台という意識づけをしていることの現れです。
言葉ひとつで意識が変わります。
就労支援の仕事において、我々は職員のことを努力の伴走者という表現をします。
あくまで努力をするのは利用者さんであり、支援員は支援するのではなく伴走するという表現をすることで支援を”やってあげている”といった勘違いを起こさせないという意図もあります。
こういった価値基準や行動基準を明確にするためにも、共通で使う言語を統一することが非常に重要と考えます。
共通感情
これは共通した感情を持てているかどうかということです。
皆で成し遂げた喜び、うまくいかなかったときの悔しさ、心無いことを言われたことときの悲しさなどなど。
また、お互いを称賛したり承認しあったりすることも大事です。
このチームにいてもいいんだ。このチームの一員なんだと全員が感情的に思えるかどうか。これが重要と考えます。
役職ではなく、役割で仕事をする
僕は非常に上下関係の厳しい高校野球部出身なのですが、年齢が一つや二つ違うだけで神様と奴隷みたいな関係でした笑
会社員は3年やりましたが、先輩というだけで偉そうな人もいました。
こういった組織やチームというのは健全な状態とは言えません。
役職があることが偉いわけではないからです。
役職でふるまいを変えている人はかなりダサイですね。かっこ悪いです。
役割が違うだけなので、上も下もないです。
だからこそ年齢や性別国籍関係なく全員に対して敬う心をもって接することが大切だと考えます。
コレクティブ・エフィカシーがある
コレクティブ・エフィカシー(集団的エフィカシー)といった表現をしますが、これは集団的自己効力感のことを言います。
自己肯定感は自分の存在を認めることができる/大切に思えるチカラであることに対して、自己効力感というのは「わたしならできる」と思えるチカラです。
ですので、集団的自己効力感というのは「私たち俺たちならできる」と思える集団的心理状態が発生しているということです。
コレクティブエフィカシーがあるチームを例に出すとすれば甲子園常連校の大阪桐蔭などでしょうか?
自分たちは日本で一番練習をしている、自分達は日本で一番強い、自分達は日本で一番選手層が厚い、俺たちが負けるはずがない。
こういった感情がチーム全員で持てていると思います。
こういった集団的自己効力感を得るためには
①チームとしての小さな目標を達成し続ける、小さな成功体験を積み重ねる
②各メンバーが自分の役割を認識し、その役割に応じた責任を背負って行動できている
こういったことが重要になってきます。
まとめ
共通目標、共通言語、共通感情があるか
役職ではなく、役割で仕事をする
コレクティブエフィカシーがある
みんなでいいチームをつくっていこう!
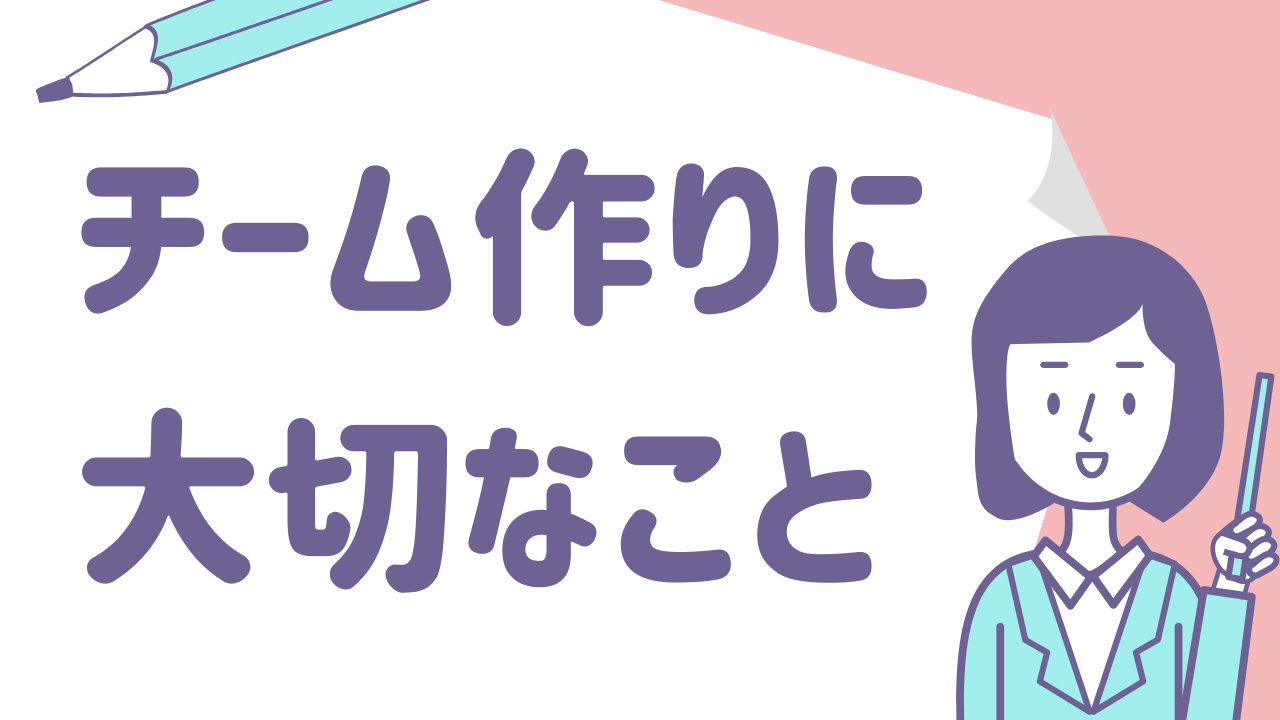
コメント